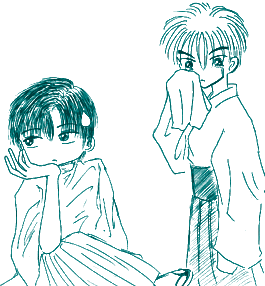十八日月
雨。僕は本堂から桂の枝に注ぐ雨を眺めていた。
晴れていれば見えるはずの居待月。しかし、今日は月を見る気にはなれなかった。雨に感謝しなければならないだろう。
「どうかしたのかよっ?」
僕をのぞき込んだ真樹の目が、涙で潤んでいた。
「真樹こそ、どうした? 何か?」
「あのなぁ…夜見のせいだろうがっっ。さっき親父と神卸の修行してたんだよっ。やっと呼吸のリズムができた途端、夜見と同調しちまったのっ! 何だよこれはっっっ。涙も止まらねーし、もうサイテー…」
溢れる涙を拭いながら、真樹は僕のとなりに座った。
「そうか、真樹が同調して悲しみを引き受けてくれたのか」
だから懐かしさだけを思い出せたのだろう。
「せめて、理由ぐらい教えろよ。こんな…くそっ、気が狂ったら夜見のせいだからなっ」
「軽口たたく余裕があるなら、大丈夫だ。もうとっくに発狂しているころだから。…それにしても、不意に千五百年分の悲しみを引き受けて、自我を保てるとは、たいしたモンだな」
真樹の生まれ持った許容量は、僕の力を越えているかもしれない。真樹は自覚していないが、斎主になる頃は、僕の力を完全におさえることも可能だろう。
「感心している場合かっっ。なんとかしろよ」
「……理由を話せばいいんだろう?……今日は、命日だ……」
長く生きていると、毎日が誰かの命日だ。それでも、やはり特別はある。
限りなく僕に近い力を持った、もう千五百年以上昔の斎主。僕が殺してしまった女性。
「ちょっとまて、斎主って、男じゃなかったのか?」
「斎主が男でなければならないと決めたのは、彼女が死んだ後だ。二度と繰り返したく無かったからな……彼女に植え付けてしまった魔は、何をしても祓えなかった…」
悲鳴をあげ、苦しみ悶えながら息を引き取った彼女。
彼女は、何かを僕に伝えていた。それによって、僕が救われていたことを知ったのは、彼女が逝った直後。
いつの間にか僕の孤独感を癒してくれていた何かが、彼女の死と同時に消失していた。
結局、神と呼ばれながら何も出来なかった僕は、自らに累積する悲しみを課した。当時は、自分を苦しめることでしか、怒りは抑えられなかった。
「……ひょっとして、夜見、その女の人のこと……」
「…………。真樹、精神集中しただけで同調できるのは能力が高い証拠だよ。ただし、高い能力には、常に大きな危険が伴っている。不要の場合は、自分からつながりを切り離す方法を見つけた方がいい」
「言うだけなら、簡単なんだよっ。 それができないから、俺はこんなことになってんだろうがっ」
だから、僕は心配せずにはいられない。もしかしたら、真樹も……。
僕を凝視したままだった彼女の死顔を思い出す。彼女の能力も、とても秀でていた。
「夜見? 急に黙り込んでどうした? 大丈夫か?」
僕の心配を知らない、のんきな言葉。まだ涙の止まらない真樹を見たら、ため息しかでなかった。
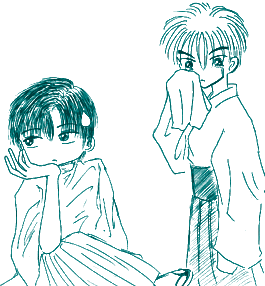
十九日月へ
月読記へ