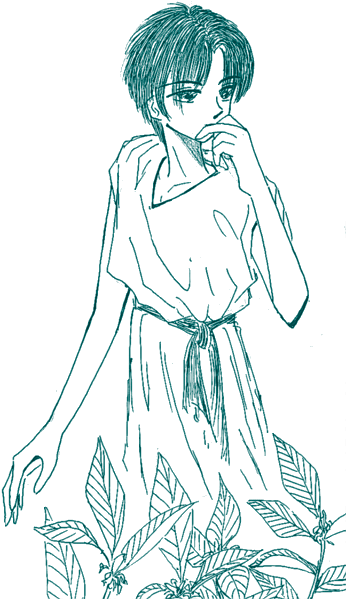二日月
消えてしまいそうな月の光。地上を照らすには、あまりにも弱い光。
「また月見てるのかよ。毎日毎日、よく飽きないよな」
母屋から、真樹がいつもの供え物を手に出てきた。
「……今夜は、星会い月の夜だ。多くの人が命を吸われる……」
静かな視線を感じて足元を見る。鳥居の笠木に座っている僕を、下で真樹がじっと見つめていた。
「どうした?」
「……やっぱり、夜見は神様なんだな。そうやってると、怖いくらい綺麗だ。俺、近寄れねーや」
真樹の声が、震えている。その表情が伝えているのは、僕に対する畏怖の念。
「ああ多分、今夜は凶月で魔が強いからだ。神酒を……」
僕は、真樹の手にした供え物の中にあった神酒を、手元へ引き寄せた。
月を長い間読み続け、既に人でなくなってしまった僕の身体は、月光の持つ性質に強く影響される。
時によって妖艶に、神聖に、穢濁に、清浄に。
「そーやって物を動かすの、なんて呼ぶか知ってるか?」
「ESP。超能力。念動力。一昔前なら、魔術。神技。もっと昔だと、まやかし。あやし……」
神酒で強すぎる魔を祓い清めながら、思いつく限りの言葉を連ねて真樹に答えた。
「あーっ、もういいっ。夜見に聞いた俺が馬鹿だった」
そんな真樹の様子がおかしくて、僕は笑いながら笠木から降りる。
真樹が恐らく無意識に、後ずさりした。
「………おい、本当に清めた? まだ、俺、寒気するけど」
「だろうな。月にあてられてかなりの魔を吸収してしまったから、この程度の神酒では祓いきれないんだよ。月水はもう終わっていたな。今夜は、本殿に戻らずここにいることにしよう。真樹は早く家の中へ入った方がいい。……いずれ僕は魔に染まる」
こんな夜、魔に染まった僕が、斎主の血族にとってどれほど危険かは、彼らの方がよく知っている。下手に近づくと、僕は望む望まずに関わらず、彼らを誘い、その身体に魔を植え付けてしまう。男性なら、まだいい。祓うことができる。でも女性の場合、祓えない。そのまま魔に耐え切れず、死んでしまう。
僕の斎主が代々男性なのは、そのためでもある。
真樹が母屋に戻るのを見届けて、僕は月を見上げた。先程清めたばかりの魔が、再び僕を蝕んでゆく。
月光の魔に酔う。嫌いな感覚ではなかった。
魔に酔っても所詮、今夜限り。明日には余韻も残らない。人には決して味わえない感覚。
僕は再び笠木に立つと、魔を迎えた。
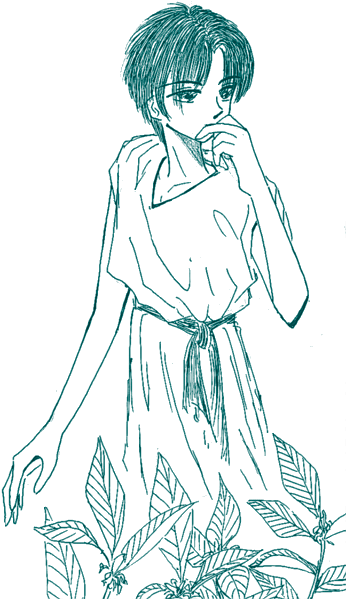
三日月へ
月読記へ