THE POWER OF PEOPLE

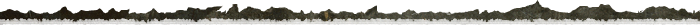
社会主義考190自立した個人の交響体人民の力代表 常岡雅雄
最も迫られているのは—代表としての常岡自身の「新々飛躍」
執筆を常岡が担当する巻頭言
その主語の言い方を変える
執筆を担当する常岡自身が自分の責任を曖昧にせず
常岡の人としての息吹きと血の脈打つ主語にする
「新しい帝国主義」への転形期に迫られる「新々飛躍」
今号の巻頭言は、今日までの普通の巻頭言とは趣の変わったことを語りたい。「語るべきだと迫られている」とも感じている。
「人民の力」は—誰でもが「新々飛躍」を心に誓っている。
一九六八年の「新たな飛躍を準備せよ!」にはじまる政治同盟「人民の力」としての政治的自覚。それから三年後の一九七一年の創立をへてはじまる「人民の力50年」の歴史—それは、「人民の力」の政治同盟としての「新たな飛躍」の半世紀であった。
当時支配的であった「旧い社会主義」から訣別して「新しい社会主義」探求の道に立った—その決断と勇気と苦闘が一度目の「新たな飛躍」であった。
そして21世紀の現在。その「新たな飛躍」の半世紀を積んで、「人民の力」は「もう一つの飛躍」を遂げて行かなければならないところに来ている—すなわち「新々飛躍」である!
そこで、その「時代的な課題」である「新々飛躍」を「代表としての常岡自身の巻頭言」でもって挑戦するとすれば、どうすればいいのであろうか?—例えば、巻頭言の「主語の言い方」を、次のような言い方に改めるのも、その一つではないだろうか。
始めるのは—先ずは「僕」から
この「人民の力」誌の「代表としての常岡が執筆担当する巻頭言」では、今後、「僕」という、一人称の「ざっくばらんな」言いかたで語りたい。
なぜ、「ざっくばらんな言い方」にするのか—「語っている僕」が「僕であるため!」にほかならない。
さて、この種の政治的な文書では、一般には、「われわれ」とか「私たち」とかが「主語」となる。
しかし、ここでのぼくは「一人の人間」として「ものを言いたい」ので、「僕自身をしめす」ところの「一人称単数形」でものを言いたい。
「一人の人間」としての「心や想いや感情」のままに「語りたい」し「語るべきだ」と思う。「一人の人間としての責任」で「ものを云いたい」し「ものを言うべきだ」と思う。
文章を「われわれ」とか「私たち」とかの「複数形で語る」とき—そこでは既に、「語る人」としての「自分自身」の「責任」とか「一人の人間」としての「責任」とかが「複数の人々」へと「スーとすり替えられ」てしまっているのではないだろうか。
無規定な主語で—責任をすり替えてはならない
「われわれ」とか「私たち」とか表現することによって、その「語っている主体」としての「自分の自身」が「自分以外の人々の陰」に「隠れてしまっている」のではないだろうか。
その「われわれ」とか「私たち」という言葉使い—それは「一人の人間としての責任の自覚」という「厳しさ」から「自分自身を逃れさせる」のではないだろうか。それはまさに「すり替えの主語」ではないだろうか。
「一人の人間」として「重く厳しく自覚すべき責任」を「自分以外の不特定の多数の人々」へと「すり替えてしまう」—それはまさに「すり替えの主語」ではないだろうか。
常岡には「常岡の血」が流れ「常岡の息吹」がある
それが「僕」なのだ
更に、常岡は「おとこ」であるから、自分自身を言いあらわすのに「僕」という—「わたし」とは言わない。
「おとこ」である常岡が、ことさら丁寧に「わたし」と「自分自身を云う」とき—それはなにやら「そらぞら」しい。「よそ行きのスーツ」をまとった「形だけの常岡」がいるだけである。その「わたし」は「生身の常岡自身からは遠い遠い遥か彼方の存在」となってしまっている。この場合の「わたし」には、「生身(なまみ)の常岡自体」の「生き生きとした血も息吹」も感じられない。
この「僕」という言い方こそ、「普通の人間」として「血の通った常岡自身」の「もっとも身近な言い方」なのである。「他の人とは違う特定の息遣いや振る舞いをする常岡」—「特定の心と想いと感情などをもった人間としての常岡」が「その自分自身」を「もっともあるがままに言い表せる」—それが「僕」なのである。
機関誌「人民の力」は創刊いらい1000号を遂に超えることができた。
一日と十五日の月二回発行で、一日号の巻頭言を「僕」が執筆担当している。一日号の巻頭言は「人民の力」創刊いらい、「僕」と共に歩きつづけてきた。そして、引き続き21世紀の今後も「僕」と共に歩きつづける。
人類世界を「自立した個人の交響体」へ
そのために「僕がある」のである
例えば、オーケストラは、様々な楽器の奏者が演じて「一つのハーモニー」をみごとに奏でる。様々な楽器の奏者は、それぞれ、自分なりの個性と考えと力量を備えている。自分なりの努力で自分の演奏力を磨いている。
それは音楽の世界における「自立した個人」の「交響体」なのである。生きた響きあいは、一人ひとりが「自立していて」こそ実現できる。
人間の世界は、もっともっと遥かに多人数であり、その各人はそれぞれに個性をもっており自立している。「人類世界を構成する人びと」の(一)「太古以来の共通した願い」であり、(二)これからの未来に向かっての「永遠の願い」であるところの「理性とヒューマニズム」を基調とした壮大な「交響体」へと複雑多様な人間世界が「進歩」していく—そのために努めるのが、「無限の未来」へと歩みつづける「人民の力」のつとめである。
確かに、膨大で複雑多様な人類世界ではあるが、この「自立した個人」の「交響体」へと緩やかではあるが流れて行っているのが「人類世界」の「大河」なのである。
その「人類世界」の「大河の流れ」が広がり汚れを清め無限に流れつづけてゆくこと—それこそが人類世界にとっての「進歩」なのである。
この人類世界の「交響体の響き」は「自立した個人」によってこそ奏でられる。個人が「自立していて」こそ交響体は生命力をもち生き生きとする。
この「交響体のハーモニー」を奏でるのは「自立した個人」にほかならない—それに「僕」が「相応しくありうる」ためには、「僕」の「巻頭言の主語」は、まさに「自立した個人」としての「自立を覚悟」した「僕」でなければならない。
その「自立した個人」に相応しく「自分のおこなうべき責任」を「僕」という「主語表現」をもって「果たす覚悟」を「僕」が「僕のもの」とすることができるとき—そのときこそ「僕」は「これからの人類世界が奏でる交響体の一員たりうる」のである。
(2014年9月21日)