THE POWER OF PEOPLE

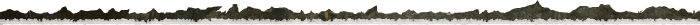
社会主義考157社会主義の新時代へ 常岡雅雄
さあ行こうー新しい時代へ
あるがままの人びとこそ
社会主義の創造者!
今日は十二月三日。新春号の巻頭言(社会主義考157)を書く予定にしている日である。
昼頃、小林栄一君と篠崎浩和君(二人とも本誌副編集長)と小林和男君(出版部長、機関誌編成室長)の三同志が新春号の発行をはじめ年末年始の諸企画の相談に、長野から横浜に私を訪ねてくる。
私は、十一月九日夜の怪我以来、通院と寝たきりの退屈な日を、三週間あまり横浜「緑園都市」の自宅で送っている。
白寿に近い二人の「おば」の死
私は、九州の大分県玖珠郡玖珠町谷口のうまれなのだが、三日前の十二月一日に、その玖珠町大隅の叔母が亡くなったとの不幸を福岡の弟が伝えてきた。
僕の母(僕は「真珠湾」の前年・昭和15年生まれの長男)は、大正3年(第一次世界大戦ぼっ発の一九一四年)生まれの98歳なのだが、弟夫婦の世話で福岡近郊の二日市の老人施設で大いに健在だ。三日前に亡くなった叔母は二日市の母の三つ年下だから、例のロシア革命の年・一九一七年生まれで、95歳まで、ほぼ一世紀をこの乱世の世界を生きぬいてきたのである。
僕の母の実家(したがって僕が昭和15年2月6日の大雪の日に生まれた家)は、山の山に張りついたような農家10戸足らずの寒村の隅にあって、母が言うには、「富山の薬売り」のような薬屋と小作をかねた貧農であった。
だから(であろうが)、母の長兄はブラジルに、次兄は満州に渡り、三兄は母の話しでは「どこに行ったか分からない—共産党にでもなったのでは?」と噂されていたということだが、家を守った四兄は、徴兵されて中国戦線で負傷して帰ってきた。母の次姉は、下関に嫁いだのだった(僕の子供心のかすかな印象では、声のやさしい、細のメガネをかけた知的なひとだった)。
「バターご飯」を教えてくれた伯母の死
今年(2011年)は、僕には不幸が続いた。大分の叔母の死に先立つ、もう一つの不幸は、大恩ある伯母(父の長兄の「連れ合い」)の死である。母と同じ大正3年(一九一四年)生まれで、97歳であった。(佐賀県)から父の「」を継いでいる長兄に嫁にきた人で、僕が物心ついた頃には、伯父と一家をかまえて、(佐賀県)駅前(国鉄、当時)に間借りして、九州電力系の電気屋をやっていた。僕はという町が好きだった。町はずれを白州の美しい小川が流れていたからであろうか、その清流の小川で四つ年上の従兄(いとこ)と魚採りと植物採集がしたくて、小学校時代の夏休みには、自宅(当時「鉄道官舎」と云って)のある鳥栖から基山に、何日間も泊まりがけできたのであった。伯母のオムライスがおいしかった。また伯母にバターご飯の魅力を教わった。(今では、その「バターご飯」の好みが次男に伝わっている。)
僕の高校時代にはその伯父一家は、基山での電気屋をやめて、鳥栖市藤ノ木の「」に帰ってきていたが、僕は鳥栖から久留米の高校に筑後川を越えて通うために、伯父夫妻と従兄の「本家」に一年間ほど下宿していた。僕は、鳥栖から久留米まで高下駄で列車通学した(当時は、それが当たり前だった)。警察官の急襲でヤミ米の袋を列車の窓から投げすてる小母さんたちの哀れな姿を今でも思い出す。
従兄は福岡の大学生になっていて、囲碁とマージャンが人並み以上に強くなっていた。今思えば、その従兄に囲碁をシッカリ叩き込んでもらわなかったのが悔やまれる。従兄は町政から市政に格上げになった鳥栖市の福祉行政に功績があって、住民から敬意をはらわれていたが、市政移行期の過労のために、定年を待たずに亡くなってしまったのが惜しまれる。
転形期に想う—去年から今年にかけての巻頭言
僕は、今年の新春号にあたって、この調子(個人史的な)で、何を語ろうとしているのか。実は僕のこれまでの人生において関係のあった人々のことを思いおこしながら、その人々にたいする僕自身(社会主義者を自認する)の考え及び行いを具体的に問い直してみたいと考えているからである。
この後、今日までの様々な人々との出会いや関係によっていろどられる僕の人生は様々に多面的に続いている。順を追って振り返れば(一)バスケット(鳥栖での中学時代)、柔道(久留米での高校時代)、ボート(福岡での大学時代)を経験したスポーツ生活。(二)横浜鶴見での鉄鋼会社員時代。(三)短期間だったが大阪での「労働運動関係の新聞」社時代。(四)賃金・労働者教育・社会保障、国労機関誌「月刊こくろう」編集、調査資料室と担当した国労本部時代。(五)その国労本部時代とダブルが神奈川の社会主義青年同盟(社青同)時代。(六)そして今日へと続く「新しい社会主義運動」としての一九七一年七月結成以降の「人民の力」時代である。
この間に、どうしても忘れられないのは、(イ)横浜・常盤台での、入社早々二年間にわたった独身寮時代(その時の同僚友人関係は、その後、「常盤会」として復活して今日も続いている)(ロ)日本鋼管の鶴見・川崎・水江の三工場および鉄鋼労連本部と、その関東地協の青年労働者たちと「テッサの会」として興した青年活動家組織の時代(ハ)全逓横浜中央郵便局の青年活動家たちとの学習会時代(ニ)僕の「連れ合い」の実家(宇都宮の農家)の物静かで知的で思いやりの深い人々との関係である。
しかし、それをここで具体的に語ることは紙数が許さない。
現実に生きる人びとを見つめてきたか?
僕は、過程で出会った人々(自分の両親も含めて)を、(一)あるがままに認めてきたであろうか? その人々の一人ひとりに、人としての歴史があり、社会があり、思いがあり、願いがあるのだということが、僕には分かっていたのであろうか? ほとんど分かっていなかったではないだろうか。「分かろう!」とする姿勢すらも弱かった—さらに詰めれば「なかった」のではないだろうか。
現実に生きるあるがままの人々が社会主義をつくる
( 二)前項で「(一)あるがままに認めてきたであろうか?」と言ったが、その「あるがまま」こそが、「きたるべき社会主義」の「実体」なのであり、(三)その「あるがまま」の「実体」を見つめ、そのうえに「きたるべき社会主義」を「構想しよう」=「構想すべきだ」—と心から考え、そのように振る舞って(実践して=生きて)きたであろうか?
僕は、このように、今までの自分を問い直しながら、この2012年新春号の巻頭言(社会主義考157)を語り始めたのであった。
野田首相がTPPへの日本としての「参加」表明をしたことによって始まった、「新しい太平洋時代」は、前々号巻頭言で言ったように「後のない」=「どん詰まり」の太平洋時代にほかならないのだが、だからこそ、その提起しているのは、僕たち社会主義者(社会主義運動)に向かっていないのである。
変わるべきときには変わらなければならない
私たちは、今までの社会主義者(社会主義運動)こそ、「後のない」時代にいよいよ入り込んだことをこそ、TPP時代の到来によって、知るべきなのではないだろうか?
今まで通りの姿勢や発想と行動方式では、TPP参加を「決断した」野田首相や日本支配階級にも及ばないことを私たち社会主義者は自覚すべきなのではないだろうか?
昨年の新春号では「夢—13か条」を語ったが、既にその発想のうちに含んでいたのだが、今年の新春号にあたっては、社会主義運動こそが(社会主義者を自認する者としての私たち一人ひとりこそが)「新次元」への「歴史的な飛躍」に「いよいよ迫られている」という予感をもって、私の新春の想いとしたい。「新たな飛躍」に今こそ前進せよ!
(12月3日)