THE POWER OF PEOPLE

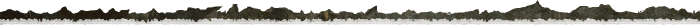
社会主義考115 秋葉原無差別殺傷事件が示すもの 常岡雅雄
人間と社会の破壊者=「資本・新自由主義・競争主義」
競争をやめ理解しあい助けあおう
6月8日 東京・秋葉原の電気街で一瞬にして7人を殺し10人に負傷させる無差別殺傷事件が起きた。派遣労働者の加藤智大(25)がレンタルのトラックで歩行者天国となっていた秋葉原の交差点に突っ込んで通行人をはね、更にダガーナイフ(短剣型ナイフ、全長約23センチ)で次々に通行人を刺して殺傷したのである。
この凶悪事件の全貌が明らかになり、犯人・加藤智大の境遇と人柄が浮き彫りになるにつれて、私は、この犯人・加藤智大が許されがたい無差別殺傷の凶悪な「加害者である」とともに、同時に「犠牲者でもある」と感じるようになった。したがって、この事件直後の本誌前号(6月15日号)の「編集長独白」で「加藤容疑者に同情する」と語った。
もちろん、私がこの無差別殺傷事件の7人の死者の一人であったならば、私は化けて出てやるほどに加藤容疑者を恨むであろう。或いは、負傷させられた10人の一人であったならば、加藤容疑者を憎み続けるにちがいない。そして、犯人・加藤智大が犯した死者7人・負傷者10人の無差別殺傷は、何ものにも替えがたい人間の生命と正常な社会のあり様にたいする許されがたい犯罪として断罪され裁かれなければならないのは当然である。
無差別殺傷を犯したこころ
こうしたことを前提としたうえで、この犯罪者・加藤智大の人柄と境遇と犯罪について思いをめぐらしてみるそうすると、犯人・加藤智大にたいして人としての同情の念がじわじわと胸の奥から滲みでてくるのを覚えるし、同時に、このような反人間的で反社会的な凶悪事件を突如として気まぐれのように犯した青年・加藤智大を生みだした今日の日本社会に重大な欠陥のあることを感じさせられる。
犯人・加藤智大が事件の数日前から携帯電話の掲示板に書き込んだ言葉は事態の意味を理解するうえで極めて重要である(朝日新聞6月10日掲載)。事件の4日前(6月5日)から事件前日(6月7日)までの4日間に書き込まれた言葉のすべては一見取りとめもないようだが、ある境遇と環境のもとにおかれた青年・加藤智大の人柄とその心の奥底から突き出てくる感情や想念として一貫した流れをなしている。幾つかの特徴的な言葉を挙げてみよう。
(5日)「作業場行ったらツナギが無かった/辞めろってか/わかったよ」「犯罪者予備軍って、日本にはたくさん居る気がする」
(6日)「あ、住所不定無職になったのか/ますます絶望的だ」「それでも、人が足りないから来いと電話がくる/俺(おれ)が必要だから、じゃなくて、人が足りないから/誰が行くかよ」「別の派遣でどっかの工場に行ったって、半年もすればまたこうなるのは明らか」「仕事に行けっていうなら行ってやる/流れてくる商品全部破壊してやる」「彼女がいれば、仕事を辞めることも、車を無くすことも、夜逃げすることも、携帯依存になることもなかった/希望がある奴(やつ)にはわかるまい」「で、また俺は人のせいにしているといわれるのか」「いつも悪いのは全部俺」「長良川越えた/堤防でいちゃついてるカップル、流されて死ねばいいのに」「店員さん、いい人だった」「人間と話すのって、いいね」
(7日)「隣の椅子(いす)が開いているのに座らなかった女の人が、2つ隣が開いたら座った/さすが、嫌われ者の俺だ」「大きい車を借りるにはクレジットカードが要るようです/どうせ俺は社会的信用無しですよ」「小さいことから『いい子』を演じさせられてたし、騙(だま)すのには慣れている/悪いね、店員さん」「『死ぬ気になればなんでもできるだろ』/死ぬ気にならなくてもなんでもできちゃう人のセリフですね」
孤独と不安と絶望の充満する高度資本主義日本
この携帯電話「掲示板」に漏らし続けている青年・加藤智大の呟きから、私たちはこの青年の存在とこの青年が犯した事態の意味の深さを理解できなければならないであろう。
犯人・加藤智大の凶悪犯行に何かハッキリとした方向をさだめた目的があったわけではない。何か具体的な結果をうみだそうとする明確な意図があったわけではない。誰か特定の人(や人々)を対象として殺人傷害を行なったわけでもない。まさに無目的・無差別の殺人傷害なのである。にもかかわらず、このような大量殺人傷害をもたらす凶悪犯罪をこの青年・加藤智大が行なったのはなぜであろうか。その意味は彼のセリフの中に秘められている。
(一)彼は親に期待され「いい子」ぶって成長してきた。その「いい子」ぶりを演じる自分を客観視し自分は欺瞞者だと自覚できるほどに鋭い感性と深い知性をもっていた。では、人間として優れた感性と知性をそなえた子どもを「いい子」ぶらせる親とは何者か。親にそのように振舞わせる教育とは何なのか。それは、本来の人間性を逆転させた、幼児の時代から大学までを一貫して全面的につらぬいて子どもたちを駆り立てている「競争主義の教育」「出世主義の教育」ではないだろうか。
(二)彼のセリフには、青年・加藤智大の心の奥底に沈殿しながら全身の皮膚感覚にまでなってしまっている「強烈な孤独感」があらわれている。彼にも同僚・家族・友人・同窓生・親類などといった人間関係が全くなかったわけではないだろう。しかし、その外面を一枚めくると、青年・加藤智大の世界は何ひとつ人間らしい声も聞こえず、微かな人間らしい肌触りも感じられない虚ろでしかなかった。彼の心はとことん孤独だったのである。
彼をそこまで落しこんだのは「競争社会の見栄や幻想にとらわれて子どもを『いい子』へと駆り立てる両親」であり「競争主義による人間破壊の教育」であり「競争主義の渦巻く冷酷社会」であり、そして、その競争主義社会で今や社会成立の不可欠の構造的要素となってしまって彼もそこに捉えこまれて翻弄され続け、心からの恋人や友人をつくる余裕も与えてはくれない「反人間的で非情そのものの派遣労働」なのである。
(三)彼のセリフには、青年・加藤智大が日々にかきたてられている「不安感や苛立ち」が滲みでている。人間の生きることにとって最も重要で不可欠の「働く場」が安定していない。企業の都合によって風に舞う落ち葉のように仕事の場を転々とさせられる。しかも、更には企業の都合によって何時でも「雇い止め」にされかねない。彼が人生のもっとも希望に満ちていていいはずの青年期の毎日毎日がこのように「風に舞う落ち葉」のような日々なのである。底知れぬ「不安感と苛立ち」に青年・加藤智大が苛まれるのは当然である。
(四)彼には落ち着いて住むことのできる住まいもなかった。家庭を営める場など全くなかった。ただ企業の命ずるままに、今日は此処、明日は彼処と転々とさせられるだけである。それでも、将来達成できるのだという希望を抱くことができたならば、その転々の流浪の旅のような辛苦の日々も耐えることができたであろう。しかし、企業の都合のままに転々とさせられる「まさに資本の奴隷」にほかならない派遣労働者がそのような希望を描くことのできるはずがない。派遣労働者としての青年・加藤智大の境遇には、将来への確かな希望をもつことも、将来への確実な設計図を描くことも与えられてはいなかった。
この資本主義日本の社会が彼にあたえた派遣労働者としての境遇が、彼の人生として、彼の将来として、青年・加藤智大に与えたものは一寸先も見えない真っ暗な絶望だけだったのである。
自分がとらわれている価値観と構造を革命する道へ
この孤独と不安と苛立ちと絶望に苛まれる日々でしかなかった青年・加藤智大には、何か狙い定めた具体的な目的があったわけではまったくない。誰か恨みをこめた特定の人物があったわけでもまったくない。ただ、科学技術と都市文明と社会経済システムと官僚制だけが反人間的・反自然的に高度に発達しながら、ひたすら競争主義と自己責任の坩堝の中に人々を落としこんで駆りたてる、この日本社会の如何ともしがたい重圧と空虚さにおしつぶされながら、青年・加藤智大は、この日本社会にたいして限りない恨みを抱いていった。その絶望と恨みの果てが秋葉原無差別殺傷という行為ではなかったのだろうか。
この犯人・加藤智大と境遇を等しくする20代から30代の「7090生」世代の若者たちが、今日、この日本社会の主流となり、労働者人口の大半を占めるようになってきた。派遣労働者であり非正規労働者でありフリーター労働者の大群である。「犯罪者予備軍って、日本にはたくさん居る気がする」という犯人・加藤智大のセリフは、今日とこれからの日本社会の価値観と構造の反人間的な本質を見事に暴いていると言わなければならない。
秋葉原無差別殺傷事件は、この日本のいよいよ度し難くのめりこんでいく「新自由主義徹底競争主義」=「資本の原理主義」という反人間的な価値観と構造を打ち破っていく道に、今日とこれからの日本を担う彼ら「7090世代」が立たなければならないこと、社会と人間を正立させていく道に立たなければならないこと、人間革命と社会革命の道に進まなければならないことを、否定的なかたちで明らかにしたのだと私は考える。
(08・06・20)