THE POWER OF PEOPLE

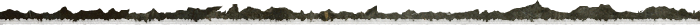
「いいだ・もも」「生田あい」両氏ら「未来」派の国鉄闘争論
無責任な「悪しき左翼主義」を批判する
国鉄労働者会議 小林栄一
私たち人民の力が、「未来派の非道理は許さない」として送った、中央常任委員会(委員長・島田英希)の2月8日付けの批判書や、私を含めた中央常任委員などの「未来」派指導部諸氏への批判書、および本誌2月15日号に発表した常岡代表の「未来」批判に対して、3月9日付けの「お返事」が届いた。そして、その「お返事」は、『未来』紙3月20日号に「協同・未来全国調整委員会」名で掲載された。
その「お返事」が、私たち人民の力の組織や個人が送った批判に明確に答えたものではなく、道理も常識もわきまえない、まさに「悪しき左翼主義」そのものであったことは、「お返事」が届いた2日後の3月20日に常岡代表が「未来」派に送った再批判(本誌4月1日号に掲載)によって明らかであり、それをここでくり返すつもりはない。
ただ私は一昨年の10月末でJRを定年退職するまで、40年余の鉄道人生をおくってきたが、その約半分を国鉄分割・民営化反対と国鉄闘争に身をおいてきたものとして、見過ごせない問題があるのでペンをとったしだいである。
それは、「未来」派が2005年7月25日付けの機関紙『未来』62号において、突如として全く一方的に私たち人民の力にたいする、いわれなき極限的な決め付けをおこないながら、「亀高・岡山・瀬尾」君たちが嘘でぬりかためてつくりあげた「人民の力改革全国協議会」への支持を、彼らを熱烈にもち上げて表明したことを、自己正当化するための理由付けについてである。
「協同・未来全国調整委員会」は、私たち人民の力には唯の一度も事実の収拾や調査を行なわなかったことは棚にあげて、「人民の力改革全国協議会」を支持した理由を二つあげている。その二つの理由が、私たちの批判に答えたものでないこと、すなわち社会主義者・組織のあり方や、手法「態度決定の姿勢の『敵対性』や、態度決定上の『方法の非合理性』」にたいする批判への答えになっていないことは、すでに常岡返書で明らかである。
ただ、その一つが、「国鉄闘争の方針転換への支持」だとして、私たち人民の力の国鉄闘争への批判を次のように行なっている。
「闘わずしての『統一と団結』『政治解決』は不可能です。しかし、常岡氏の国鉄労組政策は、国労中央執行委員会への統一と団結を強調するだけで、この国鉄闘争団の対鉄建公団訴訟闘争を無視していました。亀高氏と岡山国労を中心とする人民の力改革協議会が、この常岡中央方針を自己批判と共に転換させ、国鉄闘争団とともに対鉄建公団訴訟を闘う方針を、9・15判決以前に採択したことは、国鉄闘争を前進させる上で評価できることでした。」と述べて私たちを批判している。
20年余にわたる私たち人民の力の国鉄闘争を正確に認識し、その闘いの歴史と実態を正しく把握・分析した上での批判にはとうていなりえていないし、私たちへのその短絡的、近視眼的ないいがかりのなかに、「協同・未来」派のエセ左翼性が浮き彫りにされている。
中曽根攻撃の主的であった国労こそが当事者
具体的な批判に入る前に、事実の問題として次の点にふれておきたい。私たち人民の力の国鉄闘争方針(政策)を、「常岡氏の国鉄労組政策」とか「常岡中央方針」と記して、意図的に常岡代表「個人」の「政策」「方針」であるかに描き上げている。その方針の検討と決定を行なった人民の力の同志ひとり一人や機関を無視・欠落させ、私たちの「主体性」や「尊厳」を侮辱している。もし仮に、本当に「常岡氏の国鉄労組政策」を批判したというのであれば、2005年2月1日号の「人民の力」誌に発表した「国鉄闘争を考える(私案)団結回復をかちとり、先ずは国会前150日間絶食座り込み闘争へ」の「常岡私案」を全く見ていないかその意味を理解していないことになる。事実を意図的に捻じ曲げた中傷に外ならない。また、私たち人民の力は「国労の統一と団結」を提起はしたが、「中央執行委員会への統一と団結」を提起したことや、表明したことは唯の一度もない。
私たち人民の力は、国鉄分割・民営化を体制側の戦略的な攻撃として捉え受けとめてきた。
すなわち、1960年代中期以降の国鉄再建体制と労働戦線の帝国主義的再編・「統一」攻勢を「国労と総評労働運動」解体攻撃として捉えてきた。73、74春闘の高揚と75年のスト権ストはその攻撃に若干の歯止めをかけることはできたが、それを教訓化した体制側は、「専門懇意見書」路線をもって押しかえし、「土光臨調」を発足させ、中曽根をかついでその総仕上げとしての国鉄分割・民営化攻撃を加えてきたのである。
中曽根が後にその本質と狙いを吐露しているように、「国労をつぶし、総評をつぶす」ための攻撃であり、そのための「国鉄改革法」であった。「新会社への採用」を巧みにつかった国労への組織攻撃や弾圧がいかにすさまじかったかは、18万人国労が、新会社発足時には4万人に激減した事実をみても明らかであろう。まさに国家的不当労働行為であり国労つぶし攻撃であった(しかし、その未曾有の嵐に抗して国労は4万組織を残したのである)。
そしてまた、JR発足以降のJR会社の労務政策も、「一企業一組合」の名のもとに、不当転勤や配転、国労バッチ着用への処分の乱発と手当て・昇給カット、昇進試験差別などの国労攻撃が執拗に続けられてきた。1047名の解雇撤回闘争を除くさまざまな労使紛争が解決または和解に至ったとはいえ、その基本が変わったわけではない。JR労働運動における国労の位置は大きく後退し、その影響力も著しく低められてきたが、時の葛西職員局次長(その「功績?」をかわれてJR東海会社の社長、会長にまでのぼりつめた)が「国労をすりつぶす」と豪語した攻撃の本質は、全くかわっていない。20年を超えた国鉄闘争の困難性もまた、そこにあるのである。
たしかに1047名の解雇撤回闘争が国鉄闘争の柱の一つではあるが、国鉄闘争とはもっと総体的で、その本質は「国労つぶし」との闘いなのである。「血の入れかえ」による本務外しや不当配転・転勤、試験制度を利用した国労差別などとの闘いがそこに含まれるのは当然である(私もまた、悪名高き人材活用センターへの配属以降、電車運転士を外され、20年にわたる「元職へ返せ」の要求と運動も実らず、長野駅の売店でその鉄道人生を閉じたが)。
それゆえ、国鉄闘争の当事者とはまさに国労そのものなのである。ましてや、国鉄につづいて精算事業団からも首を切られた1047名の国鉄労働者のうち、960余名が国労組合員である。全国36の闘争団をつくり、生活と闘いを統一させて闘い続けてきた全国の闘争団と家族に、国労は全責任を負わなければならないのは当然であろう。
たしかに、既存の労働組合が闘いを放棄、または切り捨ててしまった結果、「争議団」として闘わなければならなかった事例は数多い。そして、それらの闘いが連合主導下の日本労働運動のなかで、重要な役割を果たしてきたことも事実である。しかし、国労は弱さや不十分さはあるにせよ、国労組織として国鉄闘争を闘い続けてきた。また、体制側も国労を抜きにした「解決」を考えているとはとうてい思えない。
「四党合意」をめぐる組織混乱と二分状況が、相手側をして「解決できない」理由とさせたことはまごうことなき真実である。体制側は、二分状況の国労と国鉄闘争の自己崩壊をこそねらっていたのである。
私たち人民の力は、国鉄闘争の当事者は国労であり、国労が軸に据わらない限り国鉄闘争の解決はないと判断した。その軸となるべき国労を分裂させてはならないし、闘う「統一と団結」が大切であることを私たちは主張し、そのために努力してきた。時の国鉄闘争情勢の核心はまさにその点にあったのである。
たしかに、国労はその位置と役割を自覚し、その任務を果たしてきたとはいいがたい。とりわけ、「国鉄改革法」の承認からはじまる国労の闘争指導には問われるべきさまざまな問題(例えば、「国鉄改革法」の承認や「四党合意」を数の力で強行してきたことや、一部闘争団への統制処分の発動など)があることも事実である。そして、残念ながら国労はその中心としての役割を果たし、闘いを創りあげてくることはできなかった。
その点は厳しく総括しなければならないが、国労は大衆組織として国鉄闘争を闘ってきたのであり、大衆組織のあり方として、組織を分裂させ闘いを二分させてはならないのは当然であろう。私たちは「国鉄改革法」承認にも、「四党合意」にも反対してきた。それは、国労の思想・路線にかかわる問題として捉え、体制側の戦略的攻撃に対する国鉄闘争のあり方として批判してきたのである(「国鉄改革法」承認を「苦渋の選択」として認め、その延長線上に惹起した「四党合意」には反対した人たちもいたが)。
だからといって、大会で決めた方針に従わなくていい、というような無責任で自分勝手な方針を私たちはとってこなかった。批判すべきは批判しつつも「団結」を大事にする組織原則をふまえて対応し、そのなかで闘いの前進のために奮闘してきたのである。
所謂「闘う闘争団」の問題性
それは国鉄闘争に分岐をもたらした
当時、私たち人民の力は「どっちもどっち論にたっている」などと的ハズレな中傷もされた。そして、一部闘争団(所謂「闘う闘争団」)を支持しないものは日和見だなどと無責任で傲慢な決め付けもされた。
事態を表面的にしか見ない、あるいは、単純に物事を線引きする人たちに対して、私たちは全面的な反論は行なってこなかった。二分状況の国鉄闘争の「団結の回復」と「解決実現」に向けた闘いと戦線の構築こそが大事だと思ったからである。亀裂を深めるような批判は差し控え、自ら闘うことによってその困難な事態を切り開こうと努力したのである。
私たち人民の力は、国労本部の思想・路線的後退がその根本要因であると認識し、数の力で「国鉄改革法」や「四党合意」の承認をおし進めた国労本部と国労指導にたいして一貫して批判してきた。それが私たち人民の力の基本的立場である(過去の「人民の力」誌やそれらを特集した「赤い鉄路」第25号、第26号を読んでもらえば分かる)。
しかし、私たちはその批判を組織上の問題にまで広げることには批判的である。
先にも述べたが、国労は全国36の闘争団をつくり辛苦の闘いを続けてきた。その国労闘争団全国連絡会議のなかで、「四党合意」承認を契機として一部の闘争団が一方的に「闘う闘争団」を名乗って活動を開始した。その命名自体がすでに36闘争団に亀裂をもち込むものであった。すなわち、自分たちが勝手に一方的に命名した「闘う闘争団」に組みしない闘争団は「闘わない闘争団」ででもあるかの如く線引きして戦列を二分させたことになるのである。
しかも、独自の事務所を確保し、独自の財政と、独自の指導部を選出し、国労方針とは別の道を進み始めた。その一つが鉄建公団訴訟である。それは、闘争団内部にも感情的な対立も含めて決定的な亀裂をもたらした。国労の大会などでも闘うべき相手を間違えているのではないかと思われる混乱や、ヤジなどが乱れとんだ。国鉄闘争支援の側も二分された。まさに、所謂「闘う闘争団」が独走した運動は、大衆組織と闘いに分岐と亀裂をもたらしたのである。
首を切られた当事者の組織を分裂させてはならない、という函館や筑豊、宮崎闘争団などの努力がなかったらば、友好人士からの「統一回復」への願いや努力がなかったならば、そして微力ではあれ、「統一と団結の回復」と闘いの発展を提起し、自らも決起・努力してきた私たち人民の力の奮闘などがなかったならば、国鉄闘争の現在はおぼつかない。もちろん、それとて主軸であるべき国労がストライキやハンストに決起しえない弱さによって、闘いは20年を超え、いまなお困難な状況にあることには変わりはないが。
しかし、所謂「闘う闘争団」に大衆組織における組織上の問題があるとはいえ、それをもって国労本部が行なった「統制処分」や「生活援助金の凍結」に対して、私たち人民の力は当然にも反対した。一部闘争団の鉄建公団訴訟にたいしても、その判決が国鉄闘争に与える影響を考えたとき、国労が直接関与した裁判ではないとしても無視すべきではないことを提起し、私たちが2005年の8月に行なった第1波ハンストでは、「東京地裁は『公正な判決』を行なえ」をその闘争目標の一つにかかげたのである。批判的な立場に立っていたとはいえ、「無視」するようなことは決してしてはこなかったのである。
国労委員長ハンストを
なぜ提起してきたのか
私たち人民の力は、2005年2月1日号の「人民の力」で公表した常岡代表の「団結回復をかちとり、まずは国会前150日間絶食座り込み闘争へ」が、二分状況で困難な国鉄闘争の局面を切り開く重要な提起であり方針であると確認し、その実現のために奮闘した。その闘いの頂点に国労本部委員長の決死のハンストがすわり、全国の国労指導者がその闘いに呼応してハンストに決起し、全国総がかり闘争へと発展させるべきだと提起してきた。
大衆組織の責任者が文字通り「命をかけた闘い」に決起することによって、世の中から忘れられかけている国鉄闘争に光をあて国民世論を喚起して、政府をして「解決しなければならない」と決断させる状況をつくりださないかぎり、解決局面を切り開くことはできないと判断したからである。
2002年2月に隣国の韓国鉄道労組が発電産業労組やガス公社労組とともに民営化阻止をかかげてゼネストに突入したように、国労もまたストライキに決起できればそれにこしたことはない。かつての国鉄時代のように列車を止めることはできないにしても、社会正義をつらぬく闘いとして、社会に決意と闘いをアピールできたであろう。しかし、膨大な費用と労力を要するストライキでなくとも、食を断ち、命をかけて闘う絶食闘争(ハンスト)もまた、韓国の労働運動指導者がおこなってきたように、そして、それを教訓化して全国へと波及した分割・民営化反対絶食闘争でも明らかなように、極めて重要な闘いである。
国鉄闘争を闘う労働者・労働組合のなかにあって、国労は最大組織であり、最も多くの闘争団員を組織している。その責任組合としての国労が、委員長ハンストを火柱とした全国総がかり闘争へと決起することができれば、「統一と団結の回復」はもちろん、解決局面を切り開くこともできたであろうと思っている。
そのためにも私たち人民の力は、まずは自分自身がハンストに決起すべきだと決意した。そしてこの間4波にわたるハンストを行なってきたのである。
国労大会と鉄建公団訴訟判決を目前にした2005年8月の第1波ハンストをかわきりに、国労中央委員会前段の2006年1月の第2波、ILO第7次勧告をうけ、国労訴訟が準備されていた同年12月の第3波、そして、7300人を結集した11・30日比谷集会のエネルギーを次の闘いへ継続発展させようと決起した、東京闘争団佐久間忠雄氏のハンストに連帯した2007年12月の第4波のハンストを、国労組合員・OB有志などによって長野、名古屋、米子、宮崎などで実施してきた。
残念ながら、大きな広がりへと発展させることや、われわれが求めた国労本部委員長のハンストへと昇華させることはできなかったが(2006年12月には国労本部の佐藤前委員長がハンストを決意したといわれていたが)、しかし、そのつど多くの人士や労組、韓国の労働運動闘士・李寿甲先生などからは心からの支援と連帯、激励をいただいた。「私たちの闘い」は「未来」派のような「見る思想も感性もそなえていない」人々には見えなかったであろうが、心ある人々には確実に届いていたのである。「闘わずしての『統一と団結』」などを私たち人民の力が強調していたわけでは決してない。
「未来」派を反面教師に
悪しき左翼主義には陥らない
私たち人民の力は、組合民主主義を逸脱した所謂「闘う闘争団」に批判的ではあったが、「鉄建公団訴訟を無視」してはこなかった。その後の鉄道運輸機構訴訟(3月13日に反動的な不当判決を下されたが)や国労訴訟、全動労争議団訴訟(1月23日に不法行為を認定して一人550万円の損害賠償を認めた)などにも、注意をはらい可能な支援と連帯を行なってきた。
しかし、裁判闘争は闘争戦術の一つではあっても、それが全てではない。いやむしろ、最新の「3・13運輸機構訴訟判決」にみるようにそして、1998年5月の東京地裁の反動判決と、JRの不当労働行為責任を免罪した2003年12月の最高裁判決でも明らかなように、裁判はその時々の情勢や力関係によって左右される。それを押し上げる大衆的な闘いや、世論の支持がなければ、「公正な判断」を行なわせることも難しい。7次にわたるILO勧告や多くの自治体決議を活かすためにも、社会の耳目を集め共感をひき起す闘いが当然にも必要なのである。
私たち人民の力は、国鉄労働者を中心とした全国組織ではあるが、国労内にあっては少数派であり、国労方針に影響力を行使できる位置にもいないしその力量もない。
しかし、私たちには闘争団の仲間がいる。彼らを含めた闘争団闘争の発展と前進のために、できうるかぎり努力を行なってきた。いかに微力であれ、国労と国鉄闘争の強化・発展のために全力で奮闘してきた。
「協同・未来」派は、国鉄闘争に直接には責任のない遠い立場から、左翼ぶって左肩をあげて私たち人民の力を最大限に中傷している。鉄建公団訴訟を支持したか否かなどという短絡的な二分法的発想に国鉄闘争の外側から安易にこりかたまって、他者の実際の苦闘や努力を見ようともしない。
これこそが「悪しき左翼主義」であり、私たちが絶対に陥ってはならない反面教師である。「未来」派には他者を批判するに値する実態も見識もない。未来派にあるのは、傲慢で独善的な姿勢と皮相な観点と「我田引水」のセクト主義だけである。「未来」派が問うべきは、何よりもまず「未来」派自身である。
(4月7日)