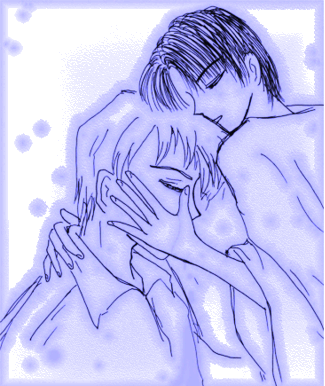一定の月日が経つと、斎主の視界から僕は消える。
本殿の扉を開ける。
「やめてくれ、夜見。まだ…もう少し1人で居たいんだ……」
部屋の隅で、うつむいたまま顔を上げない信志。彼のまわりを、動揺と混乱と悲しみが取り巻いていた。
「夜見……、もう…おれは……」
信志に歩み寄ると、そっと頬に触れる。僕の親指を、涙がつたわって流れていく。
彼は、泣いてくれていた。
僕のために。
だから、彼の頭をかかえるようにそっと抱きしめて、僕は囁いた。
「わかったから、信志。僕はここにいるから。…見えるものだけが、全てじゃない」
嗚咽を漏らす信志に、僕の声は届いているだろうか。
「…突然なんだ。…昨日までは、見えていたんだ。今までのように、当たり前に、夜見の姿が…それが、今日……」
信志の手が、ぎこちなく辿るように動いて、僕の腕を掴んだ。
「ここに夜見が居るのは、判るのに、声は聞こえるのに、見えない……っ。何も無いんだ……。どうしてこんなことが…」
斎主は、僕の姿を見ることができなくなる。
「それはきっと、信志が僕のものではなくなった証拠だよ。僕は教育係でしかないから。…ありがとう、信志」
僕を見ることができなくなった信志は、弓月夜見のものになる。弓月夜見の相手を務めとする斎主に。
それは、僕の役目が終わったことを意味する。
「夜見?……」
突然、僕を見ることができなくなってしまった斎主。その心を慰めるのは、僕じゃない。これから仕える相手が、彼を癒してくれるはず。
「我が声が聞こえるなら、鏡を取るがよい、斎主よ。我が姿を見ることを許そう……」
月色の瞳を持つ弓月夜見。
「泣くでない。そのような強い想いは、そなたを慈しみ、立派な斎主へと育てた、もう1人の我を苦しませることに気付かぬか?」
顔を上げた信志の頬に伝う涙。
弓月夜見は、その涙を封じるように信志の瞼へ唇を寄せる。
ようやく雲間から現れた月は、本堂の中へも優しい光を注いだ。