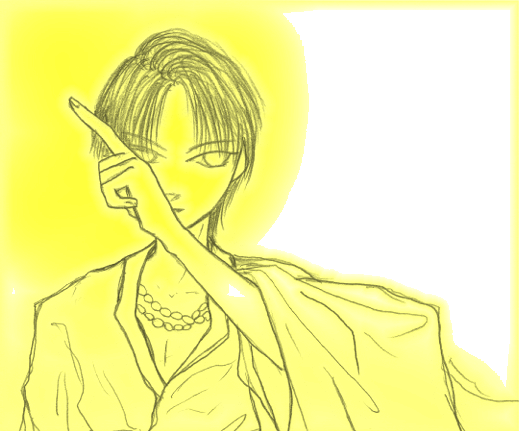追儺月
満月の夜。僕は星座の合間をぬって夜翔けを楽しんでいた。
ふと、覚えのある気配に、足元を見下ろす。以前見かけた不思議な気配を持つ男が、夜空を見上げていた。
「まだ仕事か?」
突然目の前に現れた僕に、男は驚くこともなく応じた。
「やあ、君は、いつかの…タバコの副流煙が毒だと忠告してくれた少年ですね」
「よく覚えていたな」
「職業柄、未成年の顔を覚えるのは得意なんですよ。もっとも、大人になってしまうとどうも記憶から外れてしまうようで、だめなんですけどね」
「それでは、もう二度と逢うわけにはいかないな…」
僕の苦笑に、男は怪訝な顔をした。
けれども、自分の驚きや疑問は全て押し殺したかのような、空気に交わろうとするかのような気配はそのままだ。
「そうか……。お前は…医者だな?」
この男を頼る人々の幻影が、纏わりついている。
この男の人懐っこさとは相反する幻影たち。
「似たようなものです。心の、ね」
微妙に月色に変わる僕の瞳に、男の好奇心と畏怖ととまどいが見えた。
「それはまた、大それた医者だな」
「まったくです。しかも、自覚症状のない患者がほとんどですから」
「人が人にできることは少ない。だが、悲観することもなかろう。神もまた全ての者を救うことはできぬのだからな。まあよい、我の気を惹いた幸運に免じて、お前に最近憑いていたものを祓ってやろう」
「?」
男に纏わりついていた他人の幻影を一薙ぎした。
人は時に悩みや心配事を分かち合うという表現を使う。それはある意味、正しい。
悩みを聞いた人間は、いつしか他人の悩みを自分のものにしてしまうこともある。この男のように。
「あまり自分を無力だと感じるものではない。苦しくなったら、月を見上げるが良い。我が加護してやろう」
おそらくは、弓月夜見の、ほんの気まぐれ。けれど、神は言葉を違えない。
「君は……」
男の言葉を聞かずに空に駆け上がった僕は、不思議そうに満月を見上げる男を見下ろす。
「………」
視線を星座へうつす。僕は、再び満月を浴びた風を楽しんだ。
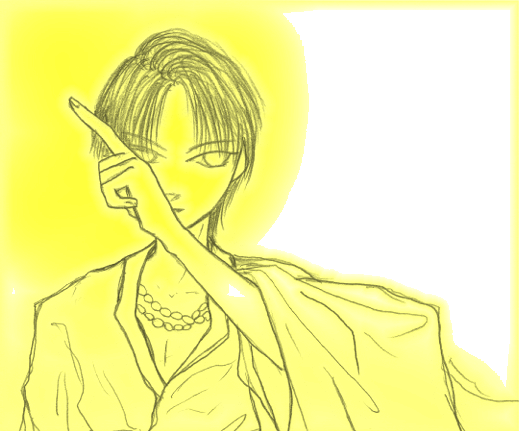
月読記へ