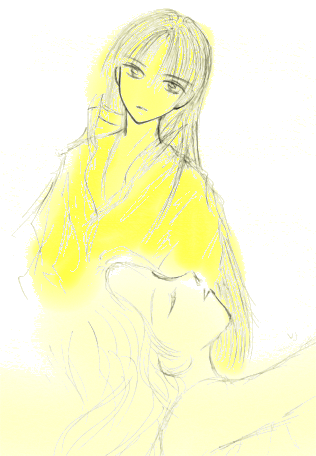遠い昔、僕を祖とする月一族の姫が居た。
両親を早くに失い孤児になった彼女を僕は訪れ、天を読む術を与えてしまった。
ほんの一時の憐れみと加護。
星の行方を読み、月の形から日を数え、多くの人々に暦を知らせた彼女は、その力を欲した多くの権力者に求められ、金品を贈られた。
天文の知識が、政治に大きく関与した時代。
彼女を引き取った家は栄え、けれども彼女は僕を忘れることもなく、夜毎に月を見上げて僕を呼び、涙を流した。
僕の意図は、彼女もわかっていた。
彼女の命数があまりに短かったから、ほんのすこしの間、かつて僕を奉っていた一族最後の一人に、憐れみと加護を与えたに過ぎない。
次に彼女を訪れるのは、彼女の命数が尽きる時。それは、彼女に預けた知識を返してもらう時。
あまりの人々の信頼と支持と栄えに危惧を抱いた当時の天皇は、幾度も彼女に忠告する。
天皇のためにその力を使えと。
やがて、すべての忠告を無視した彼女に、朝廷は兵を送り家を取り囲んだ。
彼女が外へ出ることの無いように。誰も彼女の力を求めることができぬように。
彼女が同じような力を持つ子を残すことができぬように。
それから数日後の満月の夜、僕は彼女を訪れる。
「…そうして、かぐや姫は、月の国へ帰ってゆきました」
物語が終わり、しばらく会話が続いたあと、ようやく斎主は母屋から現われた。
「遅かったな」
「すまない、夜見。なかなか寝なくて、結局最後まで読むことになってしまったよ」
「ここでも聞こえた。退屈はしなかったから、まあいいさ。そろそろ、神酒が欲しいな」
次期斎主がまだいない状態の現在、供物を届けるのは斎主の役目。
「ああ、これから持ってくるよ」
踵を返して母屋へ戻る信志を見送って、僕は仮に遇した夜の姫君を懐かしく思い起こした。