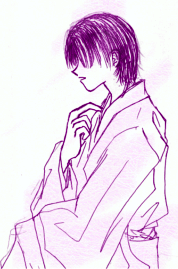花宴月
十六夜を「いざよい」と呼ぶ理由は、月が昇る時間にある。
満月よりも一刻ほど遅れて影を落とす月。
「十六夜の月」を現代の言葉に直すなら「さあ、夜になったのですからいらっしゃいな、の月」とでもなるだろうか。
今宵は桜咲く十六夜。
目覚めたばかりの僕の目の前に、信志が酒瓶を置いた。
「本当は、きれいな化粧箱もあったが、目を離した隙にコイツが散々遊んでくれて、ヨレヨレになってしまったよ…」
苦笑して片手に抱いた息子を見下ろす。1歳になろうかという真樹は、好奇心旺盛だ。最近は、どんなものでも口へ運ぶ。
見て、触り、舐め、噛み、自分の周囲の世界を確かめていく時期。
何も知らず、貪欲に知識を吸収し、言葉を会得し、日々成長していく時期。僕には、そんな時期がとても羨ましい。
「これは…趣のある酒だな。買って来たのか?」
酒瓶に印刷された絵柄と文字。十二単に身を包んだ姫君と『十六夜の詩』の銘。
「いや、今日来た参拝の方が、月神様に捧げてください、と置いていったんだ。なんでも、土手沿いの道は、桜が満開だったそうだ」
僕は酒瓶を手に取った。澄んだ液体に宿る、贈り主の想いを見透かす。
「善意と好意。いい酒だ」
杯に注がれた芳香は、待ち焦がれる恋心を彷彿とさせた。信志のひざの上に座っていた真樹が、横から手を伸ばして酒瓶に触れる。
「こらっ、やめないかっ」
「別にいいさ。確かに触れたくなるような芳香だ。十六夜は恋人を誘う夜。詩は誘い唄。名をもらった酒が、相応の性質を得たようだな」
心なしか、境内の風まで色艶を含んで僕を誘っているようだ。十六夜の詩。
春は、多くの生き物達にとって、恋の季節でもある。
甘く誘うような捧げものは、僕を存分に愉しませてくれた。
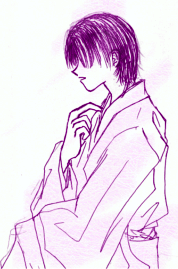
月読記へ