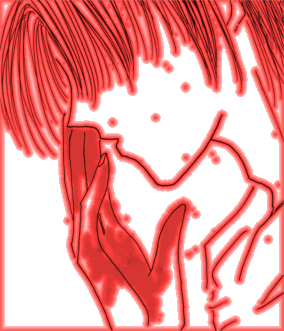紅染月
紅の月。朝日や夕日の朱色と違って、月の緋色は厭われる。
なぜなら、闇夜に浮かぶその色が、血を想い起こさせるものだから。
「なあ、夜…見……」
何か話そうとした真樹が、息を呑んだ。
「どうした?」
「悪ぃ、俺、自分の部屋に戻る……」
小さくそう告げると、一度も振り返らずに、真樹は母屋へ去ってゆく。
「……。なるほど。真樹には、見えている訳か……昔は見えていなかったのにな……」
僕は、呟きながら両手を見た。
今にも滴り落ちそうな鮮血にまみれた指先。
妖しく濡れているように見える僕の手。
現実には、何もついていない。僕の記憶が見せている、幻影。
真樹が、僕にしか見えないはずの幻影まで見るようになったのは、ここ最近のはずだ。
弓月夜見は、荒ぶる魂。人を殺したことがある。引き裂いたことがある。
月が紅に染まるとき、僕はその記憶を思い出す。月の影響を受けた幻影を見る。
「わかっていても、こう避けられてしまうと、つらいものがあるな……」
人と同じ感情を持とうとするから、傷つく。
ならば、僕は眠ってしまえばいい。僕は、次期斎主の教育係のようなものだ。
次期斎主がいなければ、月を読むのは、弓月夜見でもかまわない。
「………。血の記憶……か」
月色に変わる瞳が、赭く染まる。嫌悪感の中にある快楽が、呼び起こされる。
「哀しい性よの。斎主を呼ぶのも、癪に障るわ」
本堂の石段にうずくまる。
自分の犯した罪を忘れることが許されないほど、残酷なことはない。
快楽にでも身を沈めてしまわなければ、生きてゆけない。
「不老不死では、生きているとは言えないがな…」
初めて手を血に染めた想いに苛まれながら、弓月夜見は斎主にしかできない癒しを求め、信志の名を呼んだ。
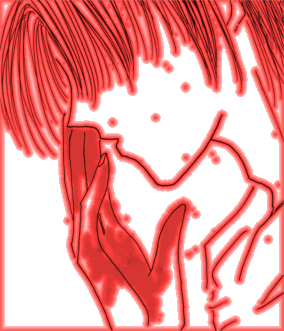
月読記へ